学校生活
【シネマ倶楽部】『ANIMAL ぼくたちと動物のこと』鑑賞文
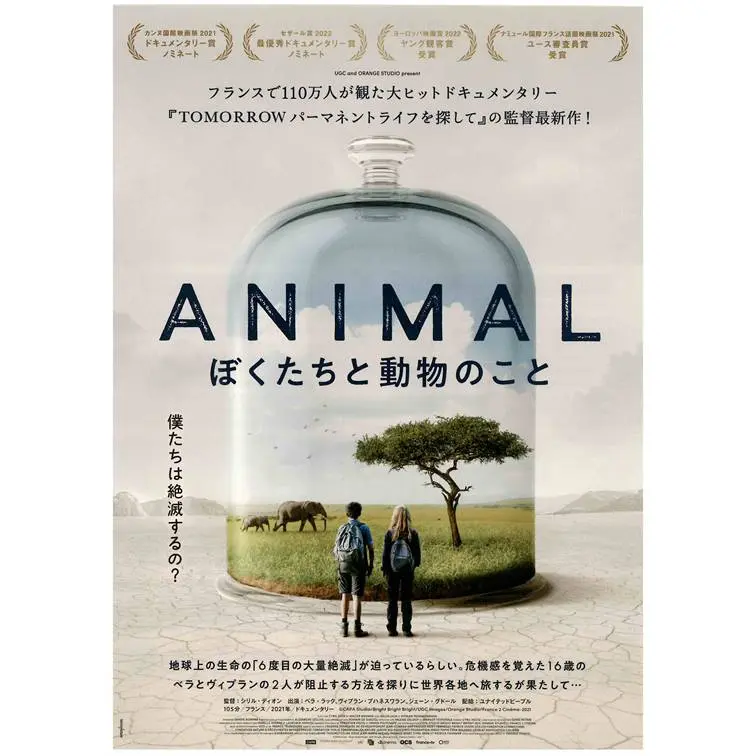
6月11・12日に中学1~3年生が『ANIMAL ぼくたちと動物のこと』を鑑賞しました。
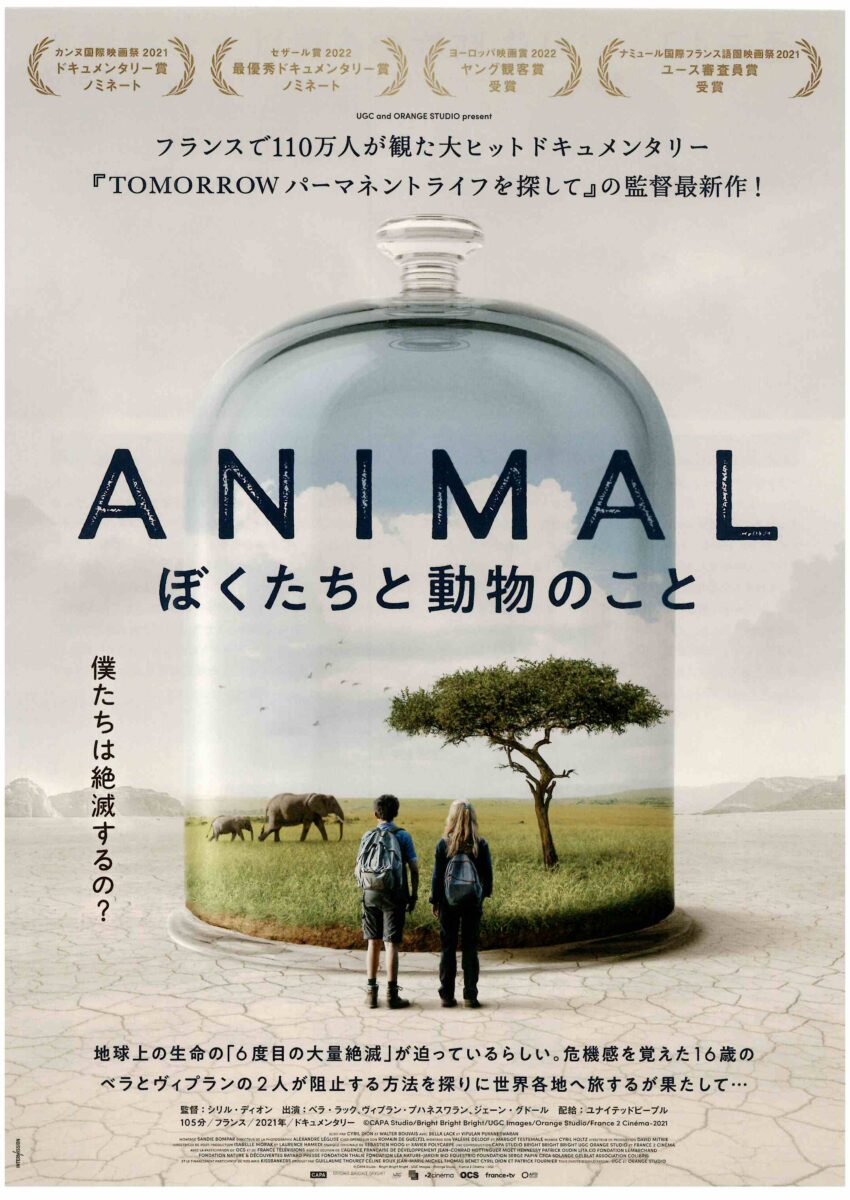
(作品概要)
ベラとヴィプランは、動物保護と気候変動問題に取り組む16歳のティーンエイジャー。自分たちの未来が危機にさらされていると確信している世代だ。過去40年間に絶滅した脊椎動物の個体数はすでに60%以上と言われ、ヨーロッパでは飛翔昆虫の80%も姿を消した。気候変動と大量絶滅を訴えるべく、2人は環境保護団体などと関わってきたが、どれもうまくいかない。そこで映画監督で活動家のシリル・ディオンに後押しされ、これらの答えを探しに2人は世界各地を巡る旅に出る。
古生物学者からは種の絶滅の5つの原因を教えられ、インドの海岸ではプラスチック汚染について知識を深め、フランスでは畜産業の実態を、ベルギーでは魚の乱獲問題を、動物行動学者からは動物と人間の関係について学んでいく。また、ケニアの大草原では野生動物に出会い、環境大国コスタリカでは大統領から自然再生のノウハウを学ぶ――。
2人は果たしてよりよい未来のための解決策を見出せるのだろうか? フランスで110万人が観た大ヒットドキュメンタリー。
- 生徒の鑑賞文には映画の内容も含まれますのでご注意ください。
(J3G Sくん)
自分はこれまで、ヨット帆走・総合・海洋人間学の振り返りで「人間と自然が共に手を取り合って、共に暮らす必要があると思う」のように、環境問題に対して、ただ人と自然が協力し合えばいいのではないかと思っていた。けれど、今回の映画を通して自分が考えていた理想は、とても困難であると感じた。困難な要因として、「人の生活と一つ一つの生き物の命、どちらが大切なのか」ということが上げられると思う。
例えば、この映画の中で魚の乱獲問題を止めるために、漁業の補助金を廃止するという意見があった。けれど、経済的な利益が最重視される国際社会で、補助金の廃止をすることは、補助金で漁業が成り立っている漁師の生活を困難にしてしまう。生き物を守ることも大事だが、人の生活を守ることも必要である。そのジレンマが環境問題の困難な要因の一つでもある。他にもウサギの大量生産では、ウサギ一匹が用紙のA4サイズとほぼ同じ広さの檻に入れられていた。そのような姿に対してベラとヴィプランは、「もう少し広い場所に入れられないのか」と述べていたが、魚の乱獲の補助金と同様、ウサギによって生活が成り立っている人は、多額のお金があるわけではなく、生きるためにウサギを育てている。生き物の命を守るにも、人間の生活が深くからみ合っていることが感じられる。
このように環境問題は、人間の活動・生活に深く結びついていることが分かった。もちろん自然を守ることと人を守ることがどちらもできるならば、それがベストだと思う。しかし、「4回目の絶滅の危機」がせまっている中、自然を守ろうとすると、人への考慮が難しい。“自然を守りたい”けれど、“人も守りたい”、これが環境問題の難しいところなのだと映画を通して思った。

